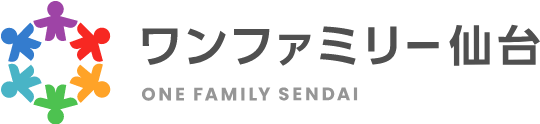メールニュースの
配信登録
月1回ほどのペースで、メールニュースを配信しています。配信を希望される方は以下のフォームよりご登録ください。
- 配信の解除はいつでも可能です。
- 費用は発生しません。

今後おきうる大規模災害にそなえよう!
ワンファミリー仙台では、休眠預金を活用して「災害ケースマネジメント」という被災者支援の手法を全国に普及させるための取組みを行っています。
ワンファミリー仙台とNPO法人YNFがコンソーシアムを組んで実施しているもので、NPO法人ジャパン・プラットフォームを資金分配団体とする休眠預金事業(2023年度通常枠)の助成金を受けて実施しています。
今回の特集では、本事業の紹介とあわせて、「災害ケースマネジメント」の考え方などを、今月から数回にわたってシリーズで紹介していきます。
全国で今後きたる大規模災害への備えや、被災者への支援体制の構築などに興味のある行政機関や関連団体、民間の支援団体の皆さんには、ぜひぜひご参考にしていただきたいと思います!

「災害ケースマネジメント」ってなに?
ほとんどの人が聞いたことがないワードだと思います。
災害時の被災者支援の有効な手法として政府でも取り入れるなど、今注目を集めている考え方の一つです。
内閣府のサイトでは以下のように紹介されています。
「災害ケースマネジメント」とは…
被災者一人ひとりの被災状況や生活状況の課題等を個別の相談等により把握した上で、必要に応じ専門的な能力をもつ関係者と連携しながら、当該課題等の解消に向けて継続的に支援することにより、被災者の自立・生活再建が進むようにマネジメントする取組。<参考>内閣府 防災情報のページ
ぶっちゃけこれだけを見ても具体的に何をすればいいのか分かりません。
誰と誰が連携して、何を目的にどんな支援をするのか、イメージしやすいように1つの事例を紹介します。

YNFの取組み事例
ワンファミとコンソーシアムを組んでこの事業を展開しているNPO法人YNFは、これまでも全国の被災地に入り、災害ケースマネジメントに基づいた被災者支援を行ってきました。
特に令和6年能登半島地震では発災直後から珠洲市の被災地に入り、被災者一人ひとりに寄り添った相談支援活動で大きな成果をあげています。
この活動がNHKのハートネットTVで放映されましたのでご紹介します。
NHK ハートネットTV(2025.1.27放送)
~特集・能登半島地震1年 問われる災害法制度~
https://www.nhk.jp/p/heart-net/ts/J89PNQQ4QW/episode/te/JYK1Z75Z8L/※ページ中ほどの「3.時代に合わなくなっている災害救助法」からYNFが登場します。
上記で紹介したサイトでは、「災害ケースマネジメント」を以下のように説明しています。
<制度からこぼれる人を救うために、被災者に寄り添う支援>
「災害ケースマネジメント」と呼ばれる取り組みで、まず被災者の元を支援者が自主的に訪ね、その人の悩みを聞き取り、一緒に課題を整理します。
そして、それぞれの事情に合わせ、必要な専門家と連携し、時間をかけて被災者の生活再建を図るのです。
▶ここから読み取れる「災害ケースマネジメント」のポイントは以下のとおり。
●被災者への支援は「待ち」の姿勢ではなく、支援者側から積極的にアウトリーチすること。
●被災者一人ひとりに寄り添って、丁寧に悩みを聞き、支援者と一緒になって課題を整理すること。
●それぞれの事情に合わせて、その課題を解決できる専門家と連携して、伴走型で支援すること。

YNFが行う被災者支援
YNFの活動も以下のとおり紹介されています。
<YNFの活動>
活動の中心は、被災した人の元を訪ね、相談にのること。市が行った全世帯への調査を元に、気がかりな人を訪ねます。被害の程度は関係ありません。困りごとがあっても、自分から声を上げない人もいるからです。<江崎代表のインタビュー>
一軒一軒訪ねていくと、壊れたままの家に住み続けてる人とかいたりするわけですよね。そういう人は往々にして、どうしようもなくなって諦めていたりする。なので、一軒一軒聞いていかないと分からないんです。僕らはそうやって知り合うことで、じゃあこの人に対してはどういう支援をやればいいか、どういう人に来てもらってアドバイスしてもらったらいいかということを考えられるので。それで、それを実行していくと、次のステップに進めるという方がたくさんいらっしゃいます。
▶ここからもアウトリーチ型で支援を届ける意義が読み取れます。
行政が苦手とする支援者側からアクションすることが「災害ケースマネジメント」の大きな特徴です。

▶NPO法人YNFのホームページはこちらから!!
専門家との連携
NHKの記事の後半の「4.できるだけ被災者の思いに寄り添った解決策を」では、以下のストーリーが紹介されています。
●YNFの訪問相談に一級建築士と弁護士が同行。
●被災者の自宅は罹災証明で「全壊」と判定されたが、修理すれば住めるのではと、解体を迷っていた。(できれば住み続けたいと希望をしている)
●建築士が実際に調査した結果、修理すると3000万円以上かかり、現実的ではないことが分かる。
●母屋の隣にあった納屋を調べると被害が少なく、修理費用は母屋の半額程度で済み、夫婦で暮らすには十分な間取りもとれることが判明。
●被災者の夫婦は納屋を修理して暮らすことに決め、地元で住み続けたいという希望が叶う結果となる。
<専門家と連携する効果>
このケースでは建築士が同行しなければ専門的な判断はできず、夫婦の希望は叶いませんでした。
また、再建にかかる資金面や隣家との問題を抱える場合は、弁護士が被災者の希望にそうように相談にのります。
災害ケースマネジメントの基本は、できるだけ被災者一人ひとりの思いにそった解決策を「探す」ことです。
そのためには、NPOなどの支援団体が単独で対応するのではなく、士業や専門家が連携して支援にあたることが求められています。

平時からの備えを!
YNFの活動を通して「災害ケースマネジメント」のポイントを紹介してきました。
被災者の希望にそった生活再建をサポートするためには、被災者一人ひとりの課題や悩みに対し、その気持ちに寄り添い、士業や専門家と連携しながら、伴走型で包括的なサポートをコーディネートするような役割が求められます。
そのためには、災害が起こる前から、行政機関や社会福祉協議会、士業などの専門家グループ、そしてNPOなどの支援団体がネットワークをつくり、連携体制を構築しておく必要があります。
この平時からの備えこそが大事であり、そこに「災害ケースマネジメント」を全国に普及させる意義があるのではないかと考え、私たちはこの事業に取り組んでいます。
ワンファミの取組み
ワンファミでも、能登半島地震の被災者の生活再建を支援するための活動を展開しており、過去2回の特集記事で紹介しました!
こちらもまさに「災害ケースマネジメント」に基づいた被災者支援であり、石川県から託されている事業です。

ご支援のお願い
ワンファミでは、このように生活困窮者支援だけでなく、被災者の生活再建や、未被災地での事前復興に資する活動を実施しています。
しかし、今回の事業だけでは、被災者の支援や災害への備えは不十分であり、行政サービスだけではカバーできない民間による支援が今求められています。
能登半島地震などにより自宅が被災し、住まいと希望を失いかけた方々が自立に向けて歩み出せるように、皆さまから温かいご支援をお願いいたします。
▼▼▼ご寄付の窓口▼▼▼
https://onefamily-sendai.jp/support
<次回のお知らせ>
今回は「災害ケースマネジメント」って何?をテーマに、その特徴やポイントの一部を紹介させていただきました。
次回の特集ではこの「災害ケースマネジメント」の考え方を広げるために、ワンファミとYNFはどんな取組みをしているのか、具体的な活動内容を紹介していきます。お楽しみに!!

この事業は休眠預金を活用した公益民間活動として、助成金を受けて実施しています。
・実行団体名:NPO法人ワンファミリー仙台、NPO法人YNF
・事 業 名:被災地を中心にした災害ケースマネジメントのOJTおよびOFF-JT研修事業
・指定活用団体名:一般社団法人日本公益民間活動連携機構
・資金分配団体名:特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム